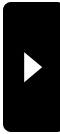› 豊田でみる、つくる、たべる日々 › とうげい
› 豊田でみる、つくる、たべる日々 › とうげい2012年12月28日
食べられない鏡もち
今年初め、飾る時期を少しだけ過ぎてから完成した粘土の鏡もちを忘れずに出してきました。のせる台がないので、足助の骨董屋さんで三方でもないかしらと出かけたら休業していて、代わりに商店街の別のお店でこんなのを見つけてきました。

一緒に行った友人うーさんによれば、ひな祭り用の道具のひとつだとか?そう言われればそんな気も・・・。でも、鏡もちにもぴったり。正月の雰囲気になってきました。
一緒に行った友人うーさんによれば、ひな祭り用の道具のひとつだとか?そう言われればそんな気も・・・。でも、鏡もちにもぴったり。正月の雰囲気になってきました。
2012年12月24日
蓋付き物入れ
先生に作ってもらった蓋付きの物入れ2種類。私は色を決めました。





ひとつには化粧水用コットンを入れようと思っています。

ひとりの先生がブタの持ち手を、もうひとりの先生が竹の持ち手をつけてくれました。
ひとつには化粧水用コットンを入れようと思っています。
2012年12月23日
新しいゴハン茶碗
カアサンがぼくに陶芸教室で新しいゴハン茶碗を作ってくれた。これまではずっとプラスチックのタッパー容器だったよ。
全神経を集中させて「よし」が聞こえるまで待つボク

「よし」! それぇ~!! カッカッカッ

カッカッカッ

ペロペロペロ おっ、前のプラスチックと違って勢いよくなめても動かないよ、このうつわ

トーサーン、食べちゃった・・・

ここからはカーサン登場。これは思いつきで、こんなふう↓に作ったものです。左上から時計回りの工程。
赤で記した場所にヒビが入りやすく、そばで見ていた先生が、「おもしろい(考えだ)けど、ちょっと厳しいよ」と言いながら、一生懸命フォローしてくださったおかげで形になりました。ちょうど、1食分ぴったりのサイズに仕上がったのはラッキでした。ガツガツして食べこぼすかな?と思ったけど、ドライフードに限っては今のところ大丈夫です。色はもっと明るい緑を狙ったのですが、外れました。


1食分がちょうどよいサイズ。灰皿にもよさそう。

全神経を集中させて「よし」が聞こえるまで待つボク
「よし」! それぇ~!! カッカッカッ
カッカッカッ
ペロペロペロ おっ、前のプラスチックと違って勢いよくなめても動かないよ、このうつわ
トーサーン、食べちゃった・・・
ここからはカーサン登場。これは思いつきで、こんなふう↓に作ったものです。左上から時計回りの工程。
赤で記した場所にヒビが入りやすく、そばで見ていた先生が、「おもしろい(考えだ)けど、ちょっと厳しいよ」と言いながら、一生懸命フォローしてくださったおかげで形になりました。ちょうど、1食分ぴったりのサイズに仕上がったのはラッキでした。ガツガツして食べこぼすかな?と思ったけど、ドライフードに限っては今のところ大丈夫です。色はもっと明るい緑を狙ったのですが、外れました。

裏側です。
1食分がちょうどよいサイズ。灰皿にもよさそう。
2012年12月08日
冬色の花瓶と小皿
陶芸教室のあちらこちらには、作品が散在?しているのですが、そのひとつに目をつけて「先生、あぁいうの、私も作りたいです」と申しましたら、その作品を型にして先生がちゃ、ちゃ、ちゃ、と作ってくれちゃいました。この教室では、いつもこんな感じです。私が手を加えられたのは、釉薬をかけるところだけ。手本とした作品は先生の作品でした。色もできるだけ近づけて、さらに、肩のところだけ薄い水色をかけてみました。先生がやったように、直後に自分でも作ってみたいのですが、時間が足りません。また、同じものを2つも3つもは要らない・・・という事情もあり、なかなか上達しないですが、その場で作るところが見られて、少しでも作品に関われれば、微々とではありますが、何か身についているでしょう、ということで。

冬っぽい色合いです。同じ色合いで小皿もできました(これは自作)。豆皿よりは深みがあるので、毎朝のヨーグルトにも使えそうです。

冬っぽい色合いです。同じ色合いで小皿もできました(これは自作)。豆皿よりは深みがあるので、毎朝のヨーグルトにも使えそうです。
2012年11月10日
オレカップ
寒い季節にオレ(俺じゃなくてau lait)を並々と入れるのが似合うみたい(もともとは蕎麦猪口として作った)。フランス人に負けないくらいたっぷり入る 。
。

 。
。木の模様は、1本1本、粘土を細くしてくっつけて・・・の作業でした。
2012年10月28日
フグと水挿し
フグかな?教室にあった型で作った皿の焼き上がり。

こちらは四角い器。

立たせて中に何かを飾って使おうと思って作りました。手前は同じ釉薬をかけた水挿し。

裏は、溶けた釉薬が窯の中で床板と剥がれなくなり、むりやり剥がした結果、あわれな姿に。立てて使えば裏面で見えにくいのでなんとか使う。

一輪の花に助けられる水挿し

こちらは四角い器。
立たせて中に何かを飾って使おうと思って作りました。手前は同じ釉薬をかけた水挿し。
裏は、溶けた釉薬が窯の中で床板と剥がれなくなり、むりやり剥がした結果、あわれな姿に。立てて使えば裏面で見えにくいのでなんとか使う。
一輪の花に助けられる水挿し
2012年10月18日
水挿しからペン立てへ
春には明るいビオラで飾ったこの水挿し。もとはガレージで部品を整理したりするのに作られたようですが、私が横取りしました。

今度はよりどりみどりのペン類を仕分けるためのペン立てにしてみたら、あら、使い勝手がよさそう。仕事から帰宅した夫も、「おっ!人間国宝の作品が使われてるぞ 」とうれしそうでした。
」とうれしそうでした。

そしてこれまでペン立てとして使っていた私の作品は、糸巻き入れになりました。糸を引き出しやすくするのには、ある程度の重さが必要なんだけど、これは陶器だから文句なしに合格。直径も深さもちょうどいいみたい。

モノにぴったりの使い途が見つけられるとうれしい(家の中でガラクタ化しているモノを見るのはつらい)。
今度はよりどりみどりのペン類を仕分けるためのペン立てにしてみたら、あら、使い勝手がよさそう。仕事から帰宅した夫も、「おっ!人間国宝の作品が使われてるぞ
 」とうれしそうでした。
」とうれしそうでした。そしてこれまでペン立てとして使っていた私の作品は、糸巻き入れになりました。糸を引き出しやすくするのには、ある程度の重さが必要なんだけど、これは陶器だから文句なしに合格。直径も深さもちょうどいいみたい。
モノにぴったりの使い途が見つけられるとうれしい(家の中でガラクタ化しているモノを見るのはつらい)。
2012年10月12日
こんな時のため
こんなとき、瓶に入れようとして砂糖や塩が瓶の外へこぼれる・・・のが嫌で作ってみたのが発端の片口。作っているうちに、どぶろくも入れたい・・・などと考えましたが。


あらしおは摩擦があって、なかなかスルスルと瓶へ落下しなかったから、結局指で手伝ったけれど、それでも一切こぼれはなし。なかなかgood。

あらしおは摩擦があって、なかなかスルスルと瓶へ落下しなかったから、結局指で手伝ったけれど、それでも一切こぼれはなし。なかなかgood。
2012年09月28日
母セレクト
前回に続いて母に手作り陶器をもらってもらいました。自分の手元を離れると何をもらってもらったか忘れてしまい、それも淋しいので写真に残すことにしています。

左上の失敗作は、「これに少し水を入れて植物を入れたりして使えるよ」と勧めたら、その気になってくれました。右下はひょうたんの形に光が浮かびあがる茶香炉。ぜひ茶香炉の香りを体験してもらいたくて勧めました。
左上の失敗作は、「これに少し水を入れて植物を入れたりして使えるよ」と勧めたら、その気になってくれました。右下はひょうたんの形に光が浮かびあがる茶香炉。ぜひ茶香炉の香りを体験してもらいたくて勧めました。
2012年09月08日
2012年08月27日
2012年07月29日
夏色の器
今回焼きあがった新しい器。残念ながら2つは失敗。

失敗その1。色合いはとても好みだったのに、残念。


失敗その2。その1もその2も、食器としてではなく、木の実でも入れよう。

これは、以前作った同じ大きさの黒バージョン。用途が広い大きさです。

一方、こちらは無事完成をみた器。これも用途が広そうです。


サラダ、一人分のつけ麺の麺、スープ、カレー、鍋物の取り皿・・・いろんなものに、ちょうどよさそう。
失敗その1。色合いはとても好みだったのに、残念。
失敗その2。その1もその2も、食器としてではなく、木の実でも入れよう。
これは、以前作った同じ大きさの黒バージョン。用途が広い大きさです。
一方、こちらは無事完成をみた器。これも用途が広そうです。
サラダ、一人分のつけ麺の麺、スープ、カレー、鍋物の取り皿・・・いろんなものに、ちょうどよさそう。
2012年07月03日
キクの明かり
竹筒花器に庭のキクを。アジサイが終わり始めると、キクが咲き始めると覚えました。

明かりが必要なほど、どんより暗い朝に、花の明かりがぽっ。キクの次は、ヤブカンゾウを活けてみたいです。今はまだ小さいつぼみ 。
。
明かりが必要なほど、どんより暗い朝に、花の明かりがぽっ。キクの次は、ヤブカンゾウを活けてみたいです。今はまだ小さいつぼみ
 。
。2012年06月25日
渋栗焼けました
栗が渋い色に焼きあがりました。

茶は栗の茶色にとても近い!まだらに見えるのは、ひしゃくでかけ流した釉薬の塗りの厚さが部分ごとに違ったからだそうです。

フリーハンドで切り出したけど、3枚がほぼすっきりと重ね合わさります。食器棚のスペース節約!

大きさ的には、、、(大きめな)ミニチュアダックスフンドと並べると、これくらい。

食べ物をのせたほうが分かりやすいですね。栗の箸置きは益子の宿『益子時計』のギャラリーで購入したもの。

茶は栗の茶色にとても近い!まだらに見えるのは、ひしゃくでかけ流した釉薬の塗りの厚さが部分ごとに違ったからだそうです。
フリーハンドで切り出したけど、3枚がほぼすっきりと重ね合わさります。食器棚のスペース節約!
大きさ的には、、、(大きめな)ミニチュアダックスフンドと並べると、これくらい。
食べ物をのせたほうが分かりやすいですね。栗の箸置きは益子の宿『益子時計』のギャラリーで購入したもの。
2012年06月25日
2012年06月14日
2012年06月06日
2012年05月29日
2012年05月27日
連珠文の数と月の向きが・・・
倉敷で見たものをそれぞれ一面ずつ描いた、思ひ出ランプ(キャンドルホルダー)の途中経過です。これは、素焼き前の、粘土が乾燥した状態。

擬宝珠(ギボシ)の向こうに見えるのが、瓦紋↑。

ギボシの左隣の面↑は、倉敷のカフェ『珈琲館』の入口にあった門扉のデザインの一部を拝借。


先生、私はこの向きにしたかったの・・・。でもまぁ、どんな向きでも三日月は三日月だからなんとかセーフか。
さらに・・・瓦紋の外側の円形模様を連珠文、内側の模様を巴紋と呼ぶそうなのですが、その数が11個しかありません。本来は12個。ここも、先生に手伝ってもらったとき、穴と穴の距離が近すぎて12個はムリになって、最終的に仕方なしに11個開けていただいたのでした。私が下絵をフリーハンドで書いているから、起こるべくして起こった事態かもしれません。予想していなかったことがいろいろ起こります。

さぁ、次回どんな色を着けようか。一面ずつ、違う色にしようかな。
擬宝珠(ギボシ)の向こうに見えるのが、瓦紋↑。
ギボシの左隣の面↑は、倉敷のカフェ『珈琲館』の入口にあった門扉のデザインの一部を拝借。
瓦紋の左隣は三日月。三日月は『はしまや』の路地で見たランプから。
しかし・・・一面一面をつないで立方体にする作業を先生がして下さったのですが、そのとき私はうっかり目を離しているときがあったのでしょう。三日月の配置が90度時計回り方向に回転し過ぎているのに今日気付きました。

先生、私はこの向きにしたかったの・・・。でもまぁ、どんな向きでも三日月は三日月だからなんとかセーフか。
さらに・・・瓦紋の外側の円形模様を連珠文、内側の模様を巴紋と呼ぶそうなのですが、その数が11個しかありません。本来は12個。ここも、先生に手伝ってもらったとき、穴と穴の距離が近すぎて12個はムリになって、最終的に仕方なしに11個開けていただいたのでした。私が下絵をフリーハンドで書いているから、起こるべくして起こった事態かもしれません。予想していなかったことがいろいろ起こります。

さぁ、次回どんな色を着けようか。一面ずつ、違う色にしようかな。

 。型があったから押し当てるだけだけど、やってみたら意外と愛嬌のあるサカナでした。
。型があったから押し当てるだけだけど、やってみたら意外と愛嬌のあるサカナでした。
 。
。 になった栗の実をモデルに、お皿にしてみました。
になった栗の実をモデルに、お皿にしてみました。